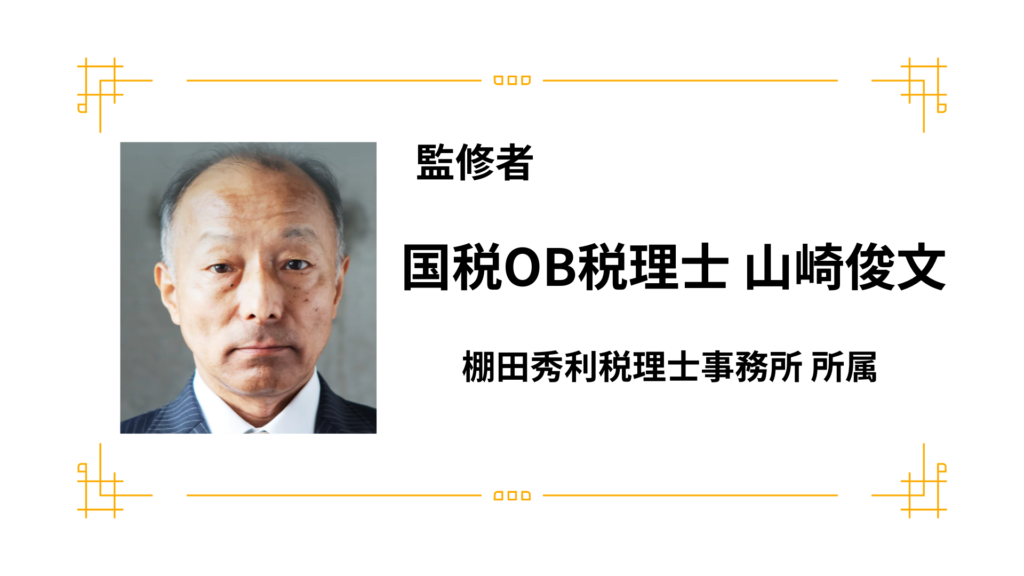相続した土地の売却時の税金は?シミュレーションと節税対策を紹介
相続した土地の売却時の税金には、大きく分けて5種類があります。具体的な計算式を用いてシミュレーションしておけば、どれほど税金がかかるのかイメージがつかみやすく、いざとなったときにも焦らずに済むでしょう。
本記事では、まず土地の売却時にかかる税金を詳しく解説した上で、具体的な税金のシミュレーションをしていきます。土地の売却を考えていているが、具体的にかかる税金やその後の確定申告の仕方に不安があるという方は、ぜひ参考にしてください。
土地の売却時にかかる税金と計算方法
まずは、相続した土地の売却時にかかる税金の種類を把握しておきましょう。土地の売却時にかかる税金は、大きく分けて5種類です。
- ● 印紙税
- ● 譲渡所得税
- ● 住民税
- ● 復興特別所得税
- ● 登録免許税
相続手続きが終わっていない場合、相続登記に必要な登録免許税も追加でかかります。譲渡所得税が発生する場合、復興特別所得税が2013年1月1日~2037年12月31日の期間で適用になります。これらの税金について、わかりやすく説明していきましょう。
印紙税
不動産の売買契約書を作成する際に、印紙税がかかります。印紙税とは、契約書や領収書などの文書を作成した場合に課税される税金のことです。国税庁により印紙税額が定められており、書類に記載された契約金額により、かかる印紙税額は異なります。
また、令和9年3月31日までは、軽減税率が適用されています。軽減前の本則税率と、軽減後の税額は以下のとおりです。〔※2〕
| 記載された契約金額 | 印紙税(本則税率) | 印紙税(軽減後) |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
〔※2〕参考:国税庁|不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
※一部抜粋
不動産の売買では「売買契約書」の作成だけでなく、所有権を移転させる登記の際に「売渡証書」を作成することもあります。どちらも不動産の譲渡に関する契約書のため、課税対象の文書です。
譲渡所得税
譲渡所得税は、相続した不動産を売却した利益にかかる税金です。譲渡所得を計算したうえで、土地の所有期間により決められている税率を掛け算し、譲渡所得税を導き出します。
譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。
〔譲渡所得の計算方法〕土地の売却金額 − (譲渡費用 + 取得費)
計算式の中で出てきた「譲渡費用」と「取得費」は、以下の内容となります。
| 譲渡費用 | 売却のためにかかった費用のこと。 ・仲介手数料 ・印紙税 ・測量費 など |
| 取得費 | 土地の購入にかかった費用のこと。 ・土地の購入額 ・手数料 ・登録免許税 など |
譲渡所得がわかったら、土地の所有期間で決められた所得税の税率を掛け算し、譲渡所得税を計算しましょう。
〔譲渡所得税の計算方法〕譲渡所得 × 所有期間に応じた税率
所有期間に応じた税率は、以下のとおりです。
| 種類 | 土地の所有期間 | 所得税の税率 |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% |
土地の所有期間で注意すべきなのが、親が所有していた期間から現在までを「土地の所有期間」とするところです。親の所有期間も引き継ぐという点を、理解しておきましょう。
住民税
相続した土地の譲渡所得に対して、住民税も支払う必要があります。住民税の計算方法は、以下のとおりです。
〔住民税の計算方法〕譲渡所得 × 所有期間に応じた税率
所得期間に応じた税率は、以下を参照してください。
| 種類 | 土地の所有期間 | 住民税の税率 |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 9% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 5% |
復興特別所得税
復興特別所得税とは、2011年3月31日に起こった東日本大震災で被災した地域の復興を支援するための税金のことです。財源確保を目的としており、2013年1月1日から2037年12月31日の期間に譲渡所得税が発生する場合、支払うこととなります。
復興所得税の税率は一律2.1%となっており、計算方法は以下のとおりです。
〔復興所得税の計算方法〕譲渡所得税 × 税率2.1%
譲渡所得ではなく「譲渡所得税」を使って計算するという点、間違えないように注意しましょう。譲渡所得税の計算方法は前項で記載していますので、そちらを参考にしてください。
登録免許税
登録免許税とは、土地の名義変更(登記)の際にかかる税金のことです。法務局に支払います。相続した土地が被相続人のままであると、土地の売却はできません。
売却するタイミングで名義変更も行わなければならない場合、名義変更時にかかる登録免許税の支払いも必要です。登録免許税の計算方法は、以下のとおりです。
〔登録免許税の計算方法〕固定資産税評価額 × 0.4%
固定資産税評価額は、市区町村などから毎年4月ごろに送られてくる固定資産税納税通知書に記載されています。通知書を紛失したなどで確認が難しい場合、役所の固定資産課税台帳で確認も可能です。
相続した土地を売却する際にできる3つの節税対策
相続した土地の売却時にかかる税金について解説してきました。これらの税金は、特例制度を正しく活用することで節税できます。
- ● 取得費加算の特例を活用する
- ● 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を活用する
- ● いつでもできる節税対策を怠らないようにする
これらについて、ご紹介します。できる限り少ない税金の支払いで済ませるためにも特例制度を知り、しっかりと節税対策をしていきましょう。
取得費加算の特例を活用する
取得費加算の特例は、相続開始の翌日から3年10か月以内に売却すれば、相続額の一部を取得費にできるという制度のことです。
取得費は土地の購入にかかった費用のことであり、譲渡所得費を計算する際に必要な費用です。譲渡所得費は課税対象であるため、相続額の一部を取得費にできることで節税になります。
特例を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
〔特例の適用を受けるための要件〕
- (1)相続や遺贈により財産を取得した者であること。
- (2)その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
- (3)その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
- (引用:国税庁|No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)
相続した本人であり、相続開始の翌日から3年10か月以内に譲渡して相続税を支払っている人が対象になる特例です。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を活用する
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例は、相続で取得した土地や家屋などを売った際、定められた期間・要件に当てはまる場合に譲渡所得から最高で3,000万円まで控除できる特例のことです。
期間と要件については、以下のとおりです。
〔期間〕
- ● 平成28(西暦2016)年4月1日から令和9(西暦2027)年12月31日まで
- ※ただし、令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡かつ相続人の数が3人以上の場合は2,000万円までの控除となる。
〔敷地や建物の条件〕
- ● 特例の対象となるのは「被相続人居住用家屋」
- ※「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住用に供されていた家屋(※家屋に対する条件もあり)
〔要件〕※多くの適用条件があるため一部抜粋
- ● 昭和56年5月31日以前に建築された家屋で譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすこととなったこと。もしくは、相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行ったこと。
- ● 売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。
- ● 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
- ● 売却代金が1億円以下であること。
- (引用:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)
期間・条件・要件に当てはまれば、大きな節税となります。
いつでもできる節税対策を怠らないようにする
節税対策として大きく2つの特例を挙げましたが、特例を活用しなくてもできる節税対策があります。主に以下の3つです。
- ● 取得費がわかる資料を用意する
- ● 譲渡費用の計上漏れをなくす
- ● ふるさと納税を活用する
譲渡所得税の計算では取得費と譲渡費が必要になります。
まず、取得費がわからない場合、売却金額の5%相当額を取得費にできます。しかし、本来の取得費よりも高い金額が取得費となってしまいかねません。取得費には、登記費用や仲介手数料・司法書士への手数料なども含まれます。明確な取得費がわかれば、それだけで大きな節税となる可能性があるのです。
さらに、売却時の仲介手数料や印紙代・鑑定料・広告料など、さまざまな経費が譲渡費として計上できます。漏れなく計上することで、節税につながります。
そのうえで、譲渡所得にかかる所得税と住民税は、ふるさと納税の利用で節税が可能です。
これらのいつでもできる節税対策を怠らないようにすることで、経済的な負担を軽くできる可能性が高まります。漏れのない申告が難しいと感じるような場合には、専門家への相談を視野に入れてもよいでしょう。
税金のシミュレーション
相続した土地の税金がいくらになるのか、以下3つの具体例を元にシミュレーションしていきましょう。
- ● 相続した土地(不動産)の実際の「取得費が不明」な場合
- ● 「相続税の取得費加算」を適用する場合
- ● 「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を適用した場合
条件は、以下の内容で解説します。
- ● 土地の売却額:5,000万円
- ● 取得費:不明
- ● 所有期間:5年以下(所得税の税率30% / 住民税の税率9%)
- ● 特別控除:なし
当てはまる状況の項目を、参考にしてみてください。なお、本記事では2023年3月現在の情報に基づいた計算を採用しています。
相続した土地(不動産)の実際の取得費が不明な場合
相続した土地の実際の取得費が不明なうえ、相続税がないと仮定したシミュレーションの項目や計算式・実際の金額は、以下のとおりです。
| 項目 | 金額 | 計算式 |
| 収入金額(土地売却額) | 5,000万円(①) | 計算なし |
| 取得費 | 250万円(②) | ①×5%(不明のため概算取得費で計算) |
| 印紙税 | 2万円(③) | 計算なし(国税庁により定められている) |
| 譲渡費用 | 100万円(④) | 売却のためにかかった費用。仲介手数料や印紙税(③)など |
| 譲渡所得 | 4,650万円(⑤) | ①−(②+④)−特別控除額 |
| 譲渡所得税 | 1,395万円 | ⑤×所得税の税率30% |
| 住民税 | 418万5,000円 | ⑤×住民税の税率9% |
印紙税・譲渡所得税・住民税の合計金額は1,815万5,000円となりました。
相続した土地(不動産)の取得費が不明で「相続税の取得費加算」を適用する場合
相続した土地の取得費は不明で「相続税の取得費加算」の特例を適用する場合のシミュレーションを行います。
まず、相続税の取得費加算は「相続税申告書」を参考にしながら計算します。必要な項目と想定金額は、以下のとおりです。
- ● 土地の相続税評価額:2,000万円(a)
- ● 売主の相続税の課税価格:6,000万円(b)
- ● 売主の相続税額:600万円(c)
シミュレーションの項目や計算式・実際の金額は以下のとおりです。
| 項目 | 金額 | 計算式 |
| 収入金額(土地売却額) | 5,000万円(①) | 計算なし |
| 取得費 | 250万円(②) | ①×5%(不明のため概算取得費で計算) |
| 印紙税 | 2万円(③) | 計算なし(国税庁により定められている) |
| 相続税の取得費加算 | 200万円(④) | c×(a÷b) |
| 譲渡費用 | 100万円(⑤) | 売却のためにかかった費用。仲介手数料や印紙税(③)など |
| 譲渡所得 | 4,450万円(⑥) | ①−(②+④+⑤)−特別控除額 |
| 譲渡所得税 | 1,335万円 | ⑥×所得税の税率30% |
| 住民税 | 400万5,000円 | ⑥×住民税の税率9% |
印紙税・譲渡所得税・住民税の合計金額は1,737万5,000円となりました。
相続した土地(不動産)の実際の取得費が不明で「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を適用した場合
相続した土地の取得費は不明で「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったとき」の特例を適用する場合のシミュレーションを行います。シミュレーションの項目や計算式・実際の金額は以下のとおりです。
| 項目 | 金額 | 計算式 |
| 収入金額(土地売却額) | 5,000万円(①) | 計算なし |
| 取得費 | 250万円(②) | ①×5%(不明のため概算取得費で計算) |
| 印紙税 | 2万円(③) | 計算なし(国税庁により定められている) |
| 譲渡費用 | 100万円(④) | 売却のためにかかった費用。仲介手数料や印紙税(③)など |
| 特例による控除 | 3,000万円(⑤) | 「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったとき」の特例を適用 |
| 譲渡所得 | 1,650万円(⑥) | ①−(②+④)−特例による控除額⑤ |
| 譲渡所得税 | 495万円 | ⑥×所得税の税率30% |
| 住民税 | 148万5,000円 | ⑥×住民税の税率9% |
印紙税・譲渡所得税・住民税の合計金額は663万5,000円となりました。
相続した土地の売却タイミングはいつが適切?
相続した土地の適切な売却タイミングは、土地活用の予定があるか、または経済的な余裕があるかによって異なります。
土地などは所有しているだけでも固定資産税の支払いが必要です。早めに売却することで受けられる控除もあるため、土地活用の予定がないならば早めに売却することをおすすめします。
ただし、土地の売却額は市場や日本全体の経済状況などで変化します。売却額の高まるタイミングで売却ができれば、大きな利益になる可能性もあります。土地活用をしつつ売却のタイミングを見計らえるくらいの経済的余裕がある方は、すぐに手放さなくてもよいでしょう。
相続した土地を売却したら確定申告が必要
相続した土地を売却し利益が出る場合には、確定申告が必要です。
- ● 土地の売却益が出たら確定申告が必要になる
- ● 確定申告は売却した翌年の2月16日~3月15日に行う
- ● 確定申告が必要かどうかは控除前の金額で判断する
確定申告に対して、注意すべき3つのポイントを解説します。
土地の売却益が出たら確定申告が必要
相続した土地を売った際に「売却益」が出たら、確定申告が必要になります。売却益は「譲渡所得」がプラスになった場合を指し、計算式は以下のとおりです。
〔譲渡所得の計算方法〕土地の売却金額 − (譲渡費用 + 取得費)
上記のとおりで売却の金額すべてではなく、売却益に対して所得税がかかります。売却したら必ず確定申告を行うわけではないという点、理解しておけるとよいでしょう。
確定申告は売却した翌年の2月16日〜3月15日に行う
相続した土地に利益がでて確定申告が必要な場合は、売却した翌年に確定申告を行います。2024年6月1日に土地を売却し、売却利益が出たと仮定しましょう。この場合は、2024年2月16日~3月15日の期間内に確定申告を行わなければなりません。
確定申告に必要な書類を揃えたら、以下いずれかの方法で申告ができます。
- ● 税務署に持参する、もしくは郵送
- ● インターネットに接続できるパソコンやスマートフォンなどで提出
確定申告するための書類は、少々難しく感じる場合があります。早めに準備を始めるだけでなく、必要があれば専門家を頼ることもおすすめです。
確定申告が必要かどうかは控除前の金額で判断
相続した土地を売却する際には控除が適用になる場合がありますが、確定申告は「控除を適用しない譲渡所得金額」で判断します。
例えば、特例により3,000万円の控除が適用になり、譲渡所得がマイナスになったとしても確定申告は必要です。
そもそも、特例・控除を適用するための条件として、確定申告が必須条件です。譲渡所得がマイナスとなった場合、控除が適用になった前後どちらの金額かどうか、必ず確認するようにしましょう。
相続した土地を売却した際の税金は複雑になりがちなので専門家に相談を!
相続した土地の売却時の税金は、印紙税・譲渡所得税・住民税の大きく3種類です。それぞれに計算式があり、計算式に当てはめていけば金額のシミュレーションも可能です。しかし、相続書類や用語は難しく、そもそもどこを見ればよいのかなどわかりづらいと感じる方も多いのではないでしょうか。
判断を間違えてしまうと正しく納税できなかったり、本当は節税できるはずの金額を見落としたりという結果になりかねません。相続した土地を売却した際の税金は複雑になりがちであるため、専門家への相談がおすすめです。
「ひろしま相続・不動産ホットライン」は相続のプロフェッショナルチームとして、税理士・司法書士・不動産鑑定士など専門家が6名在籍しています。相続した土地を売却する場合には、ぜひひろしま相続・不動産ホットラインにご相談ください。