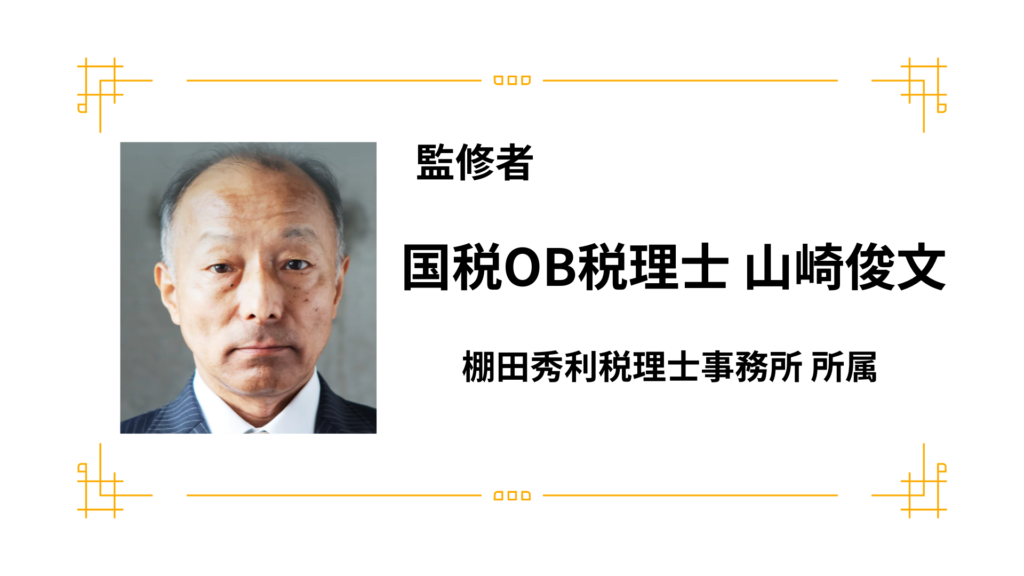未成年者控除とは?相続税の適用要件と計算方法を徹底解説
相続が発生した際、相続人の中に未成年者が含まれている場合、相続税の負担を軽減できる「未成年者控除」という制度があります。未成年者は成年者と比べて経済的な自立が難しく、今後の生活や教育に多くの費用が必要となるため、税負担を軽くする配慮がなされているのです。
本記事では、未成年者控除の基本的な仕組みから適用要件、具体的な計算方法や実務上の注意点を解説します。未成年の子どもや孫が相続人となるケースでは、適切にこの控除を活用することで大きな節税効果が見込めるでしょう。
未成年者控除とは何か
未成年者控除とは、相続または遺贈によって財産を取得した相続人が18歳未満である場合に、相続税額から一定の金額を差し引くことができる制度です。民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、2022年4月1日以降の相続については、未成年者の基準も18歳未満へと変更されました。
未成年者は経済的に自立していないことが一般的であり、相続した財産は将来の生活費や教育費として活用されるのが一般的です。相続税を満額課税してしまうと、未成年者の生活基盤を脅かす可能性があるため、税制上の配慮として控除制度が設けられています。
控除額は未成年者が18歳に達するまでの年数に応じて決定され、1年あたり10万円が控除されます。たとえば、相続時に15歳の子どもがいる場合、18歳までの3年間で30万円の控除が受けられる計算です。
未成年者控除を受けるための適用要件
未成年者控除は、すべての未成年者が自動的に受けられるわけではありません。この控除を適用するためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
・財産を取得したときに18歳未満であること
・法定相続人であること
・財産を取得したときに日本国内に住所があること
・相続または遺贈により財産を取得していること
それぞれ詳しく見てみましょう。
財産を取得したときに18歳未満であること
未成年者控除の対象となるのは、相続開始時点で18歳未満の人です。18歳の誕生日を迎えた後に相続が発生した場合、たとえ学生であっても未成年者控除は適用されません。
年齢の計算は相続開始日を基準に行います。たとえば、被相続人の死亡日が2025年10月1日で、相続人の誕生日が10月15日の場合、相続開始時点ではまだ誕生日を迎えていないため、前年齢でカウントされます。
なお、婚姻により成年擬制が適用された場合、つまり未成年者が結婚して法律上成年とみなされた場合には、実年齢が18歳未満であっても未成年者控除は適用できません。
法定相続人であること
未成年者控除を受けるためには、財産を取得した未成年者が法定相続人である必要があります。法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を持つ人のことです。
配偶者は常に相続人となり、その他には被相続人の子や直系尊属、兄弟姉妹が法定相続人となる可能性があります。たとえば、祖父が孫に遺贈で財産を残した場合、その孫が法定相続人でなければ未成年者控除は適用されません。
ただし、相続放棄をした場合でも、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を受け取った場合には、法定相続人としての地位を保持しているとみなされ、未成年者控除を適用できます。
財産を取得したときに日本国内に住所があること
未成年者控除を受けるためには、相続開始時に未成年者が日本国内に住所を有していることが原則です。ただし、日本国内に住所がない場合でも、一定の条件を満たせば控除が適用される場合があります。
具体的には、未成年者が日本国籍を有しており、かつ相続開始前10年以内のいずれかの時期に日本国内に住所を有していた場合には、無制限納税義務者として未成年者控除の適用が可能です。
また、被相続人が海外に居住していた場合でも、被相続人が日本国籍を持ち、相続開始前10年以内に日本国内に住所があった場合には、未成年者控除を適用できるケースがあります。
相続または遺贈により財産を取得していること
未成年者控除を適用するためには、実際に相続または遺贈によって財産を取得している必要があります。法定相続人であっても、遺産分割の結果として一切財産を取得しなかった場合には、控除を受けることはできません。
ただし、現預金や不動産などの本来の相続財産を取得していなくても、生命保険金や死亡退職金といったみなし相続財産を取得している場合には、未成年者控除の適用対象となります。
相続放棄をした場合でも、生命保険金の受取人に指定されているなど、みなし相続財産を取得していれば未成年者控除を適用できる点には注意が必要です。
未成年者控除の計算方法
未成年者控除の計算は、18歳に達するまでの年数に基づいて行われます。基本的な計算式は以下の通りです。
控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
計算の際には、1年未満の端数は切り上げて計算します。たとえば、相続開始時に14歳6か月の未成年者がいる場合、18歳までの期間は3年6か月となりますが、端数は切り上げて4年として計算するため、控除額は40万円となります。
具体的な計算例
実際の相続において、未成年者控除がどのように計算されるのか、いくつかの例を見てみましょう。
ケース1:15歳の子どもが相続人となる場合
父親が死亡し、15歳の子どもが相続人となった場合、18歳までの残り年数は3年です。
控除額=(18歳-15歳)×10万円=30万円
子どもの相続税額が50万円であれば、未成年者控除30万円を差し引いて、実際に納付する相続税は20万円となります。
ケース2:17歳10か月の子どもが相続人となる場合
被相続人の死亡時に相続人が17歳10か月であった場合、18歳まで2か月しかありませんが、1年未満は切り上げて計算するため、1年として扱います。
控除額=(18歳-17歳)×10万円=10万円
端数の切り上げにより、わずかな期間でも10万円の控除を受けることができます。
ケース3:複数の未成年者がいる場合
母親が死亡し、13歳の長男と10歳の次男が相続人となった場合、それぞれについて未成年者控除を計算します。
長男の控除額=(18歳-13歳)×10万円=50万円 次男の控除額=(18歳-10歳)×10万円=80万円
それぞれの相続税額から、各自の控除額を差し引くことができます。
過去に未成年者控除を受けている場合の計算
同一の未成年者が過去にも相続により未成年者控除を受けている場合、2回目以降の相続では控除額の調整が必要です。過去に控除を受けた金額は、新たな控除額から差し引かれます。
たとえば、10歳のときに父親の相続で80万円の未成年者控除を受け、その後15歳で母親の相続が発生した場合を考えます。
本来の控除額=(18歳-15歳)×10万円=30万円 過去の控除額=80万円 実際の控除額=0円(過去の控除額が本来の控除額を上回るため)
このケースでは、すでに過去の相続で十分な控除を受けているため、2回目の相続では未成年者控除を適用することはできません。ただし、2022年4月1日の民法改正をまたいで複数回相続が発生している場合には、計算方法が複雑になるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
控除しきれない場合の扶養義務者への適用
未成年者の相続税額が少なく、未成年者控除額を全額控除しきれない場合があります。このような場合には、控除しきれなかった金額を、その未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
扶養義務者とは
扶養義務者とは、民法第877条に定められた、互いに扶養する義務を負う親族のことです。具体的には、配偶者や直系血族(父母、祖父母、子、孫など)、兄弟姉妹がこれに該当します。
また、家庭裁判所の審判により特別の事情があると認められた場合には、三親等内の親族も扶養義務者となることがあります。
未成年者控除を扶養義務者へ適用する場合、その扶養義務者も同じ被相続人から相続により財産を取得している必要があるのです。
扶養義務者へ控除する場合の具体例
父親が死亡し、母親と12歳の子どもが相続人となった場合を考えましょう。
子どもの相続税額=15万円 子どもの未成年者控除額=
(18歳-12歳)×10万円=60万円 控除しきれない金額=60万円-15万円=45万円
この45万円は、扶養義務者である母親の相続税額から差し引くことができます。母親の相続税額が100万円であれば、実際の納税額は55万円です。
扶養義務者が複数いる場合には、それぞれの相続税額の比率に応じて控除額を配分することが一般的です。
未成年者控除と相続税申告
未成年者控除を適用した結果、相続税額がゼロになる場合には、原則として相続税の申告は不要です。ただし、他の特例や控除を併用する場合や、配偶者の税額軽減などを適用する場合には、申告が必要となるケースもあります。
申告に必要な書類
未成年者控除を適用して相続税申告を行う場合、以下の書類が必要となります。
・相続税申告書(第6表)
・戸籍謄本
・住民票の写し
・マイナンバーカードまたは通知カードの写し
申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると加算税や延滞税が課される可能性があるため、早めに準備を進めることが重要です。
未成年者が相続人となる場合の実務上の注意点
未成年者が相続人に含まれる場合、税務上の配慮だけでなく、遺産分割協議などの手続き面でも特別な対応が必要となります。詳しく解説します。
特別代理人の選任が必要となるケース
未成年者は単独で法律行為を行うことができないため、原則として親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加しなければなりません。しかし、親権者自身も相続人である場合には、利益相反の問題が生じます。
たとえば、父親が死亡し、母親と未成年の子どもが相続人となる場合、母親の取り分を増やせば子どもの取り分が減るという関係になります。このような利益相反がある場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。
特別代理人は、未成年者の叔父や叔母、祖父母など、相続に利害関係のない親族が選任されることが一般的です。専門家として弁護士や司法書士が選任されるケースもあります。
特別代理人の選任手続き
特別代理人の選任は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。必要な書類は以下の通りです。
・特別代理人選任申立書
・未成年者の戸籍謄本
・親権者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票
・遺産分割協議書案
・収入印紙800円分
申立てから選任までには、通常1か月~2か月程度の期間が必要です。相続税の申告期限を考慮すると、早めに手続きを開始することが重要です。
未成年者が複数いる場合の対応
相続人に未成年者が複数いる場合、それぞれについて別々の特別代理人を選任する必要があります。一人の特別代理人が複数の未成年者を代理することは、未成年者同士の利益相反となるため認められません。
たとえば、父親が死亡し、母親と12歳の長男、8歳の次男が相続人となる場合、長男と次男それぞれに特別代理人を選任しなければなりません。
胎児の相続権について
相続開始時に胎児であった子どもも、生きて生まれてくれば相続人としての権利を持ちます。民法第886条により、胎児はすでに生まれたものとみなされるためです。
胎児が無事に出生した場合、未成年者控除の適用対象となります。控除額の計算は、出生日を基準として18歳までの年数を計算しなければなりません。
ただし、死産の場合には相続権が認められないため、出生を待ってから遺産分割協議を行うことが一般的です。
孫養子の場合の2割加算との関係
孫が養子縁組により相続人となる場合、未成年者控除は適用できますが、相続税の2割加算の対象となる可能性があります。
被相続人の一親等の血族および配偶者以外が相続により財産を取得した場合、相続税額が2割加算されます。孫が養子となっている場合、代襲相続でない限り、この2割加算の対象となるのです。
未成年者控除は相続税額から差し引かれますが、2割加算は相続税額を計算する過程で加算されるため、控除額が減ることはありません。ただし、実質的な税負担が増える可能性がある点には注意が必要です。
両親が離婚している場合の対応
相続人となる未成年者の両親が離婚している場合、親権者が誰であるかによって対応が変わります。
母親が親権者であり、父親が死亡した場合、母親は相続人ではないため利益相反の問題は生じません。この場合、母親が法定代理人として遺産分割協議に参加できるため、特別代理人の選任は不要です。
一方、再婚した継親が相続人となる場合には、未成年の子どもとの間で利益相反が生じるため、特別代理人の選任が必要となります。
未成年者控除の適用におけるポイント
未成年者控除を最大限活用するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。具体的には以下の3つです。
・遺産分割における配慮
・生命保険の活用
・教育資金の一括贈与との併用
それぞれ詳しく解説します。
遺産分割における配慮
未成年者控除は、実際に財産を取得した場合にのみ適用される制度です。そのため、遺産分割において未成年者が確実に財産を取得できるよう配慮する必要があります。
ただし、未成年者の将来の生活や教育を考慮し、過度に多額の財産を取得させることが必ずしも適切とは限りません。財産管理の観点や、将来的な二次相続の可能性も含めて総合的に判断することが大切です。
生命保険の活用
生命保険金は受取人固有の財産として扱われますが、相続税法上はみなし相続財産として課税対象となります。未成年者を生命保険金の受取人に指定しておくことで、確実に財産を取得させることができ、未成年者控除の適用が可能です。
また、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、相続税対策としても有効です。
教育資金の一括贈与との併用
生前対策として、教育資金の一括贈与の特例を活用することも検討に値します。この制度を利用すれば、最大1,500万円までの教育資金を非課税で贈与することができるのです。
相続時には未成年者控除を活用し、生前には教育資金贈与を利用することで、総合的な節税効果を高めることが可能です。
まとめ
未成年者控除は、相続人に未成年者が含まれる場合に相続税の負担を軽減できる重要な制度です。18歳未満の法定相続人が財産を取得した場合、18歳に達するまでの年数1年につき10万円の控除を受けることができます。
適用にあたっては、年齢、法定相続人であること、日本国内に住所があること、実際に財産を取得していることという4つの要件を満たさなければなりません。未成年者が相続人となる場合には、税務上の配慮だけでなく、特別代理人の選任など実務上の対応も必要となります。
相続税申告は専門的な知識を要するため、税理士などの専門家に相談しながら適切に手続きを進めることをおすすめします。