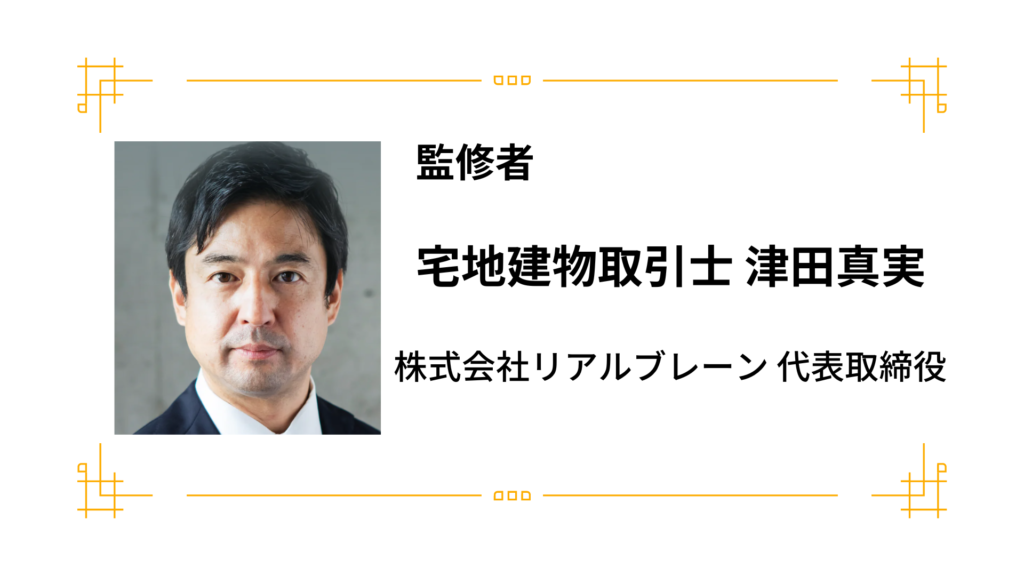雑種地の税金がかからない条件とは?固定資産税の免税点と賢い活用方法を徹底解説
相続や購入で取得した土地の中でも、雑種地は比較的自由度が高く、さまざまな活用方法が選択できる魅力的な資産となります。特に注目すべきは、一定の条件を満たせば固定資産税や不動産取得税がかからないケースがある点です。しかし、その条件や活用方法について正しく理解している方は少ないのが現状です。
本記事では雑種地に対する税金免除の条件や、おすすめの活用方法について解説します。参考にして、雑種地を上手く活用してください。
雑種地には税金がかからないケースがある
雑種地には、税金がかからないケースがあります。一般的に雑種地は、以下2種類の税金がかかるものです。
| 税の理由 | 支払うタイミング | 支払い回数 | |
| 不動産取得税 | 土地を取得することでかかる | 土地を取得した時 | 土地取得時の1回のみ |
| 固定資産税 | 土地を所有し続けることでかかる | 納税通知書を受け取ってから指定期日まで(通常年4回の分割納付も可能) | 年1回一括または年4回の分割払い |
しかし課税標準額に対する条件を満たせば片方、あるいは両方の税を免除されます。
課税標準額とは税の計算をする際、ベースとなる金額です。固定資産に関わる税においては、固定資産税評価額がそのまま課税標準額となるケースが一般的です。固定資産税評価額とは土地の価値に対する価格であるため、時価とも言い換えられます。
よって、固定資産における課税標準額は、基本的に以下のようになります。
課税標準額=固定資産税評価額=(≒土地の時価×約70%)
ただし、固定資産税評価額は実際の時価(実勢価格)の約70%程度に設定されることが一般的です。そのため、時価と完全に一致するわけではない点に注意が必要です。
雑種地の時価が30万円未満だと固定資産税はかからない
雑種地の課税標準額が30万円未満である場合、固定資産税の免税点以下となり、固定資産税がかからなくなります。
固定資産税とは、土地、家屋、償却資産(償却資産とは事業用の資産を指します)のいずれかを所有する場合に課される税金です。地方税の1種であり、毎年1月1日時点の固定資産所有状況を踏まえて、かかるかどうかが決まります。
固定資産税の計算式は、以下の通りです。
固定資産税=課税標準額×固定資産税の税率
上の計算式における課税標準額が30万円未満の場合、固定資産税が免除されるわけです。
固定資産税の税率は市区町村によって異なりますが、1.4%とされているケースが比較的多いです。
ただし雑種地以外の土地を所有している場合は、同一市区町村内の雑種地を含めたすべての土地の課税標準額を合計する必要があります。
合計の結果課税標準額が30万円未満なら免除されますが、30万円以上の場合は固定資産税がかかるため、注意しましょう。
雑種地の時価が10万円未満だと不動産取得税はかからない
雑種地の時価が10万円未満である場合、前述した課税標準額が10万円未満となり、不動産取得税がかからなくなります。不動産取得税も、地方税の1種です。
前項の固定資産税に対する免除条件は「時価30万円未満」であるため、不動産取得税の免税点の方が条件が厳しいと捉えてください。
不動産取得税の計算式は以下の通りです。
不動産取得税=課税標準額×不動産取得税の税率
なお、不動産取得税の税率は、土地の場合、2025年現在は3%の軽減税率が適用されています(本則は4%)。
また、相続により取得した土地については、そもそも不動産取得税は非課税となります。ただし、贈与や売買により取得した場合は課税対象となる点に注意が必要です。
雑種地は駐車場や資材置き場などに使われている土地
雑種地とは不動産登記に利用される地目のひとつです。
法務省は田、畑、宅地など全部で23の地目を定めていますが、雑種地を除く他22種のいずれにも当てはまらない土地を雑種地と呼びます。いわゆる「その他」に分類される土地と捉えると、わかりやすいでしょう。
具体的には、以下のような施設に使われる土地が該当します。
・露天駐車場
・資材置き場
・トランクルーム
・ソーラーパネル設置場所
・ゴルフ場
・遊園地
・鉄道用地
上はあくまで一部であり、他にも雑種地の例は存在します。
雑種地かどうかの判断には現地確認が確実
調べたい土地が本当に雑種地かどうかを判断する方法ですが、実の所もっとも確実なのは、実際に足を運んでの現地確認です。
登記簿謄本や固定資産税の課税明細書、評価証明書にも「地目」の欄はあります。しかし、書類上の情報はリアルタイムより遅れるものであり、実際の状況と食い違っているケースも少なくありません。特に登記簿上の地目と固定資産税の課税地目が異なることは頻繁にあります。同様の理由で、Google Earthの航空写真などを用いた確認も確実性に欠けます。
必ず、目で見て現地確認を行いましょう。現地確認の際は、土地の利用状況や建物の有無、周辺環境なども併せて確認することが重要です。
雑種地の活用方法5選
雑種地は、何らかの方法で利益を生むよう運用するのが大切です。ただ所有しているだけでは固定資産税などでマイナスになり、持っているだけ損になってしまいます。
具体的なおすすめ活用方法は、以下の5つです。
・売却する
・駐車場経営に利用する
・倉庫の貸し出しやトランクルームにする
・ソーラーパネルを設置する
・住宅用の宅地として活用する
上はあくまでおすすめの例です。自分の希望があれば、他の用途に使っても良いでしょう。
売却する
運用する気が無い、固定資産税などの出費を失くしたいという人には、売却してしまうのがおすすめです。該当地を不動産鑑定に出し、納得いく額であればそのまま売ると良いでしょう。
固定資産税というマイナスを失くし、売却金額でプラスにできる点が売却のメリットです。自分で運用しないため、維持費の支払いや管理の手間もかかりません。
ただし一方で、売却すれば収入はそれっきりになるデメリットもあります。運用すれば長期的な収入源にすることも可能ですが、売るとお金が手に入るのは売却時の一回だけです。また、雑種地は農地などと比べて固定資産税が高くなる傾向があるため、思うように売れない可能性もあります。
売却を検討している方は、まず複数の不動産会社に査定を依頼し、査定額を比較検討するのがおすすめです。価格に納得いかなければ、運用する方針への切り替えを検討するのも一つの方法です。なお、相続により取得した雑種地を売却する場合、相続税の申告期限から3年以内であれば「相続税の取得費加算の特例」を適用できる可能性があります。
駐車場経営に利用する
土地の面積が狭い、管理の手間がかけられないなどの場合には、駐車場経営に利用するのも良いでしょう。
駐車場経営のメリットは、管理の手間や維持費がほぼかからない点です。コインパーキングの運営会社と提携すれば、精算機や監視カメラなども設備も手配してもらえるため、運用したいが時間が無い、という人に適しています。また、駐車場経営は法律上、1台分でも車が停められれば可能です。そのため、所有する雑種地の面積が極端に狭い場合でも運用可能です。
ただし、建物が建っていないため固定資産税が高くなる傾向にあります。住宅用地の特例が適用されないため、宅地と比較して固定資産税が最大6倍になる可能性があります。加えて駐車場は、都市や観光地から離れるほど時間当たりの単価が安くなり、収入額も下がりがちです。そのため、立地によっては収支が赤字になってしまいます。
駐車場経営を行いたい場合はまず該当地周辺の状況を把握し、駐車場に需要があるかどうか確認するのがおすすめです。月極駐車場とコインパーキングのどちらが適しているかも、周辺の需要を見て判断しましょう。
倉庫の貸し出しやトランクルームにする
倉庫の貸出やトランクルームとして利用するのも、ひとつの方法です。
貸倉庫・トランクルームとして運営する場合、駐車場と同様維持費や管理の手間があまりかからない点がメリットです。また、需要が立地に左右されにくく、都市部でも郊外でも一定の利用者が見込めます。さらに駐車場に比べ、利用者とのトラブルが少なめになるのも魅力と言えるでしょう。
近年では、コンテナ型のトランクルームが人気を集めており、初期投資を抑えながら運営を開始できます。フランチャイズに加盟すれば、運営ノウハウの提供や集客支援も受けられます。
対してデメリットは、単価が安く大きな収入額が見込めないことです。固定資産税や初期投資費用と天秤にかけ、赤字にならないかどうか注意が必要です。また、少なめとはいえトラブルがないわけではなく、保管物の盗難・破損問題に対するリスクはついてまわります。
ソーラーパネルを設置する
ソーラーパネルを設置するという運用方法もあります。
最大のメリットは、生まれた電力を電力会社に買い取って貰えれば収入源となることです。固定価格買取制度(FIT)により、10kW未満の住宅用太陽光発電は10年間、10kW以上の事業用は20年間、固定価格での買取が保証されます。
一方で、初期投資費用が比較的高額になるデメリットもあります。設置する前に初期投資用の資金があるか、かけた資金を回収できるかなどの検討を慎重に行いましょう。
また、農地から転用した雑種地の場合、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)という選択肢もあります。どの手段が最適なのかは、慎重に検討して決定してください。
住宅用の宅地として活用する
住宅用の宅地として活用する方法もおすすめです。宅地とする場合雑種地ではなくなるため、土地を転用した上で運用することになります。
最大のメリットは、状況が整えば大きな収入源となることです。アパートなどの不動産経営を行えば高収入が見込めます。また、住宅用地の特例として認められれば、小規模住宅用地(200平方メートル以下)は固定資産税の課税標準額が6分の1に、一般住宅用地(200平方メートル超)は3分の1に軽減されます。
ただし無条件に宅地へと転用できるわけではなく、市街化区域内であることが基本条件となります。市街化調整区域の場合は、原則として建築行為が制限されるため、開発許可が必要です。また、不動産経営が必ず上手くいくとは限らず、赤字になるリスクもあります。
宅地として利用したいのであれば、まずは実際に宅地への転用ができるかどうかを調べましょう。その上で初期投資費用など資金面の問題と、収入を見込める見通しがあるかどうかを検討する必要があります。
なお、地目変更登記を行う際は、土地家屋調査士に依頼するのが一般的で、費用は3万円から5万円程度かかります。
相続した雑種地の税金や活用方法は専門家に相談しよう
相続した雑種地の税金や活用方法にお悩みの方は、専門家に相談しましょう。
雑種地の税金はかからないケースもありますが、実際に自分の所持している土地が該当するのかどうかは、専門家でなければ判断しきれません。また、実際に土地をどのように扱うのかも決める必要があります。
「ひろしま相続・不動産ホットライン」では、雑種地に関するお悩み解消をお手伝いできます。税金がかからないかの判断だけでなく、相続全般の悩み相談や事務手続きなども受付可能です。
現在お困りの方だけでなく、これから相続を控えており準備したい方も、ぜひお気軽にご連絡ください。