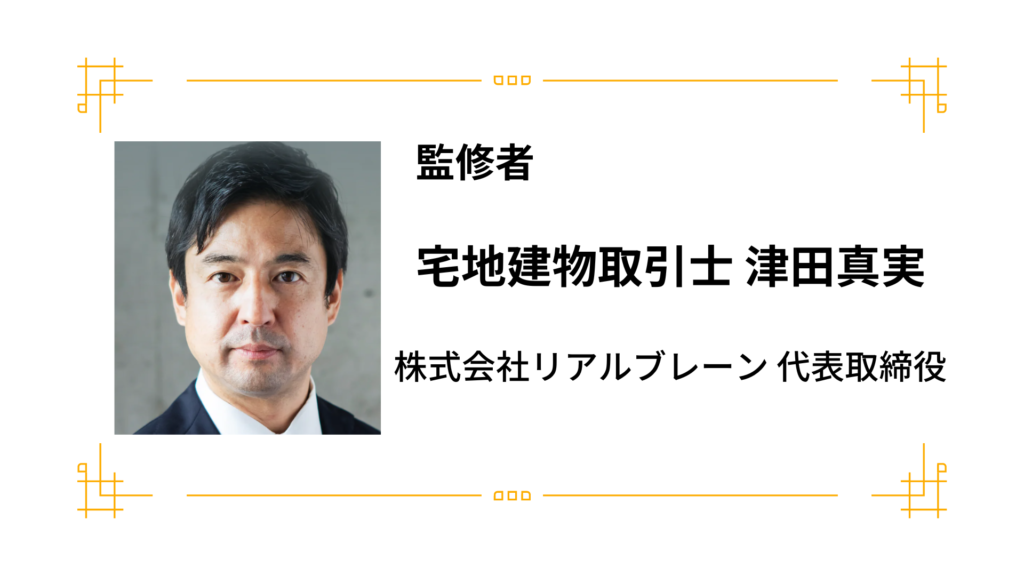相続で土地だけ放棄できない理由と対処法|不要な土地を手放す方法を詳しく解説
親から相続した土地が田舎にあって使い道がない、維持費ばかりかかって困っているという悩みをお持ちの方は少なくありません。こうした場合、「土地だけを相続放棄したい」と考える方も多いでしょう。
しかし、残念ながら土地だけを選択的に相続放棄することはできません。相続放棄は相続財産の全てを対象とするため、土地だけを放棄して現金や株式は相続するといった使い分けは不可能です。
本記事では、なぜ土地だけの相続放棄ができないのか、不要な土地を手放すためにはどのような方法があるのかを詳しく解説します。2023年4月に開始された相続土地国庫帰属制度についても触れますので、土地の相続でお悩みの方はぜひ参考にしてください。
土地だけの相続放棄ができない理由
そもそも相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が引き継ぐ制度です。この際、相続人には3つの選択肢があります。
● 単純承認:被相続人の財産と債務を全て引き継ぐ方法です。プラスの財産もマイナスの財産も含めて、全ての権利義務を承継します。
● 相続放棄:相続人としての地位を完全に放棄する方法です。被相続人の財産も債務も一切引き継ぎません。
● 限定承認:相続した財産の範囲内でのみ債務を弁済する方法です。相続人全員で行う必要があり、手続きが複雑なため実際にはあまり利用されていません。
なお、相続放棄を選択した場合、被相続人の財産を選別して一部だけを放棄することはできません。現金や預貯金、株式、不動産といった全ての財産を対象として、一括で放棄する必要があります。
これは民法の「相続人は、相続の承認又は放棄をしたときは、これを取り消すことができない」という規定に基づいています。相続の包括承継主義により、相続財産は一体として取り扱われるのです。
したがって、「土地は要らないけれど現金は相続したい」「建物は相続するが土地は放棄したい」といった選択的な相続放棄は認められていません。
遺産分割による調整は可能
ただし、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議により財産の分配を調整することが可能です。例えば、長男が土地を相続し、次男が現金を相続するといった分け方ができます。
この場合でも、各相続人は一度相続財産全体を承継した上で、その後の分割により特定の財産を取得することになります。土地を相続しない相続人も、分割が完了するまでは土地の管理責任を負う可能性がある点に注意が必要です。
不要な土地を相続するデメリット
不要な土地を相続してしまうと、次のようなデメリットがあります。
● 固定資産税の負担
● 管理費用と手間
● 損害賠償責任のリスク
それぞれ詳しく見てみましょう。
固定資産税の負担
土地を相続すると、その翌年から固定資産税の支払い義務が発生します。固定資産税は土地の評価額に応じて算出されるため、利用していない土地でも毎年税金を納める必要があるのです。
特に更地の場合、住宅用地の特例が適用されないため、税額が大幅に増加する可能性があります。住宅用地であれば固定資産税が6分の1に軽減されますが、更地では軽減措置が受けられません。
また、空き家が建っている土地でも、建物が「特定空き家」に指定されると住宅用地の特例が適用されなくなり、税負担が重くなってしまうのです。
管理費用と手間
土地を所有している限り、適切な管理を行う責任があります。草刈りや清掃、境界の確認といった日常的な管理に加え、不法投棄の防止や防犯対策も必要です。
遠方にある土地の場合、管理のために定期的に現地を訪れる交通費や、管理会社に委託する費用が発生します。年間数十万円の管理費用がかかるケースも珍しくありません。
損害賠償責任のリスク
土地の管理を怠った結果、第三者に損害を与えた場合には、所有者として賠償責任を負う可能性があります。例えば、管理不十分により土砂崩れが発生して隣接する建物に被害を与えた場合や、倒木により通行人が怪我をした場合などです。
こうしたリスクを避けるためには、適切な管理を継続する必要がありますが、そのためのコストも考慮しなければなりません。
相続放棄の手続きと注意点
相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
熟慮期間の起算点は、被相続人の死亡を知った時ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とされています。つまり、被相続人の死亡と同時に自分が相続人となったことを知った時点から3か月です。
期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなりますが、相続財産の存在を知らなかった正当な理由がある場合には、例外的に期限の延長が認められる可能性があります。
必要書類と手続き
相続放棄の申述には、以下の書類が必要です。
● 相続放棄申述書
● 被相続人の住民票除票または戸籍附票
● 申述人の戸籍謄本
● 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述書には収入印紙800円分を貼付し、連絡用の郵便切手を添付します。
家庭裁判所から照会書が送付された場合には、必要事項を記入して返送します。その後、相続放棄申述受理通知書が交付されれば手続きは完了です。
相続放棄後の管理義務
相続放棄をしても、次の相続人または相続財産清算人が管理を始めるまでの間は、相続財産の管理義務が残ります。これは民法940条に規定されている「相続放棄者の管理義務」です。
土地の場合、適切な管理を怠って第三者に損害を与えた場合には、相続放棄をした元相続人であっても賠償責任を負う可能性があります。管理義務を完全に免れるためには、相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
相続土地国庫帰属制度の活用
2023年4月27日に開始された相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈により取得した土地を国に引き渡すことができる新しい制度です。これまで土地の所有権を手放す方法が限られていた問題を解決するため創設されました。
この制度を利用すれば、相続放棄をしなくても不要な土地だけを手放すことが可能になります。ただし、対象となる土地には厳格な要件が設けられており、全ての土地が引き取ってもらえるわけではありません。
対象となる土地の要件
国庫帰属制度の対象となるのは、相続または遺贈により取得した土地です。売買により取得した土地は対象外となります。また、以下のような土地は引き取りの対象外です。
申請段階で却下される土地
● 建物がある土地
● 担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地
● 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるもの
● 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
● 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
審査で不承認となる可能性がある土地
● 崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用または労力を要するもの
● 土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上に存在する土地
● 除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることができない有体物が地下に存在する土地
●隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができない土地として政令で定めるもの
手続きの流れと費用
国庫帰属の手続きは、まず法務局への事前相談から始まります。相談では、対象となる土地の要件を満たしているかを確認し、必要な書類について説明を受けましょう。
申請時には審査手数料として14万300円を納付する必要があります。審査の結果承認された場合には、負担金の納付が必要です。負担金の額は土地の種類や面積により異なりますが、原則として20万円となっています。負担金の納付が完了すると、土地の所有権が国に移転し、手続きは終了です。
ただし、市街地の宅地や農地、森林などは面積に応じて負担金が加算される場合があります。手続き前にしっかりと確認してください。
土地を手放すその他の方法
土地を手放す方法として、相続土地国庫帰属制度以外にも以下の選択肢があります。
● 売却による処分
● 寄付による処分
● 土地活用による収益化
● 隣接地所有者への譲渡
それぞれ詳しく解説します。
売却による処分
不要な土地を手放す最も一般的な方法は売却です。不動産会社に仲介を依頼して買主を探すか、不動産会社に直接買い取ってもらう方法があります。
売却価格が低くても、固定資産税や管理費用から解放されることを考えれば、長期的にはメリットがある場合が多いでしょう。特に立地条件が良い土地であれば、思いのほか高値で売却できる可能性もあります。
ただし、市場価値の低い土地の場合、買主が見つからない可能性があります。そのような場合には、価格を大幅に下げるか、他の方法を検討する必要があります。
寄付による処分
国や自治体、法人などに土地を寄付する方法もあります。特に公共性の高い利用が見込める土地であれば、自治体が受け入れてくれる可能性があります。
一方で、寄付を受ける側にとっても管理費用が発生するため、どのような土地でも寄付を受け入れてもらえるわけではありません。寄付の可能性については、まず地元の自治体に相談してみることをお勧めします。
土地活用による収益化
売却や寄付が困難な場合には、土地活用により収益を得る方法も検討できます。具体的な例としては、駐車場や資材置き場としての貸し出し、太陽光発電設備の設置、農地としての利用などです。
土地の立地条件や周辺環境によっては、思わぬ活用方法が見つかる可能性があります。不動産会社や土地活用の専門業者に相談すれば、具体的な提案を受けられます。
隣接地所有者への譲渡
隣接する土地の所有者にとって、隣地は利用価値の高い土地となる場合があります。駐車場として利用したり、建物の建て替え時に敷地を拡張したりする用途が考えられます。
隣接地所有者であれば、市場価格よりも高い価格で購入してくれる可能性もあるでしょう。まずは隣接地所有者に購入の意向があるかを確認してみてください。
相続前にできる対策
相続前にできる対策もあります。代表的なものは、以下の3つです。
● 生前贈与による処分
● 遺言による指定
● 家族信託の活用
生前に何かしらの対策をしたい場合は、ぜひ検討してみてください。
生前贈与による処分
相続が発生する前であれば、被相続人自身が土地を処分することも可能です。売却や寄付により土地を手放すことで、相続人の負担を軽減できます。
ただし、生前贈与には贈与税が課税される可能性があるため、税務上の取り扱いについては専門家に相談することをおすすめします。
遺言による指定
遺言書を作成し、特定の相続人が土地を相続するよう指定することも可能です。土地の管理に関心のある相続人や、その土地の近くに住んでいる相続人に相続させることで、管理の負担を軽減できます。
遺言書は自筆で作成もできますが、不備があった場合に遺言の内容が無効にされてしまう恐れもあります。多少の費用が掛かりますが、相続で争わないためにも公正証書遺言で残すと良いでしょう。
家族信託の活用
家族信託を設定することで、土地の管理や処分について柔軟な対応が可能になります。家族信託とは、財産の持ち主が信頼できる家族に財産の管理や処分を任せつつ、受益者に利益を与えられる仕組みです。
被相続人が委託者となり、信頼できる家族を受託者とすれば、土地の管理を任せることができます。ただし、手続きが複雑であるため、こちらも専門家に相談することをおすすめします。
土地の相続は専門家の判断を仰ぎましょう
相続において土地だけを選択的に放棄することはできませんが、不要な土地を手放すための方法は複数存在します。2023年4月に開始された相続土地国庫帰属制度により、従来よりも土地を手放しやすくなったといえるでしょう。
ただし、国庫帰属制度には厳格な要件があり、全ての土地が対象となるわけではありません。また、土地の相続自体が複雑なものであるため、お悩みの場合は弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。個別の事情に応じた最適な解決策を見つけることができます。
不要な土地であっても、放置せずに積極的に対処することで、将来の負担を軽減することが可能です。早めの対応を心がけ、適切な方法で土地の問題を解決していきましょう。