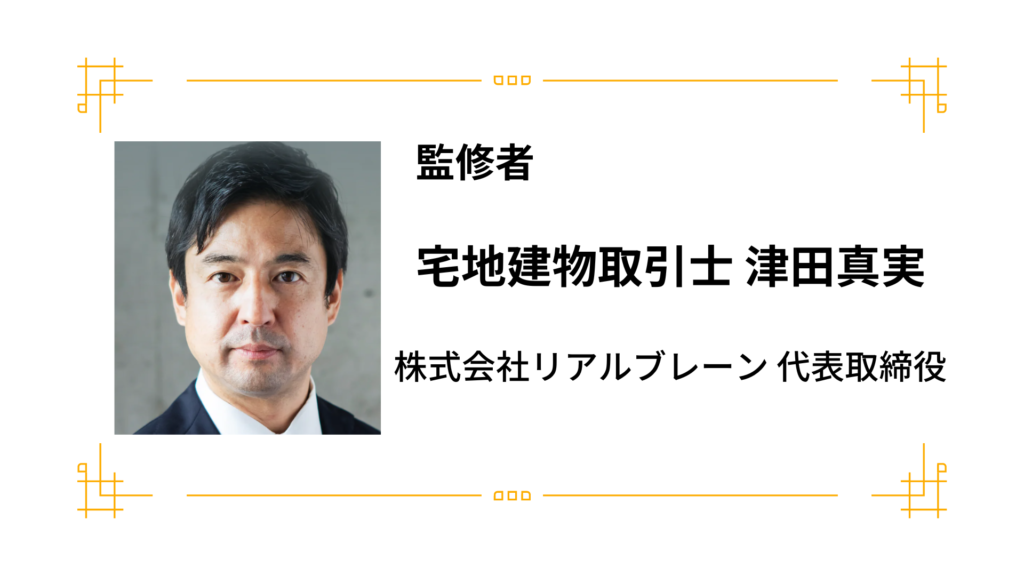相続した土地が売れないときの対処法|売れない理由と8つの解決策を徹底解説
親から相続した土地が売れずに困っている方は少なくありません。活用の見込みがない土地でも、固定資産税や管理費用は毎年発生し続けるため、多くの相続人が頭を悩ませています。
本記事では、相続した土地が売れない理由から具体的な対処法まで、専門的な視点で詳しく解説します。相続土地国庫帰属制度や相続放棄といった制度の活用方法も含めて、あなたの状況に最適な解決策を見つけられるでしょう。
相続した土地が売れないときに起こる4つの深刻な問題
相続した土地を放置していると、想像以上に深刻な問題が発生します。具体的には、以下のとおりです。
● 固定資産税の継続的な負担が発生する
● 土地の管理義務と責任がつきまとう
● 損害賠償責任のリスクがある
● 次世代へ負担を継承することになる
まずは、売れない土地を保有し続けることで生じるリスクを正確に理解しましょう。それぞれ詳しく解説します。
固定資産税の継続的な負担が発生する
土地を所有している限り、毎年固定資産税の支払い義務が発生します。都市計画税も課税対象となる地域では、さらに負担が重くなるでしょう。
例えば、評価額500万円の土地であれば、年間約7万円の固定資産税がかかる計算になります。10年間放置すれば70万円、20年間では140万円もの税金を支払うことになるのです。
売却見込みのない土地に対して、毎年数万円から十数万円の出費を強いられる状況は、家計に大きな負担をもたらします。
土地の管理義務と責任がつきまとう
土地の所有者には、適切な管理を行う法的な義務があります。草刈りや清掃、安全確保といった基本的な管理を怠ると、近隣住民からのクレームや行政指導の対象となるかもしれません。
特に山林や農地の場合、定期的な手入れを行わないと荒廃が進み、周辺環境に悪影響を与えることがあります。遠方にある土地であれば、管理のための交通費や宿泊費も発生するでしょう。
損害賠償責任のリスクがある
土地の管理を怠った結果、第三者に損害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。
例えば、土砂崩れによって隣地の建物に被害が及んだり、枯れ木が倒れて通行人にケガをさせたりした場合、数百万円から数千万円の賠償金を求められるケースもあります。
このようなリスクを避けるためには、損害保険への加入も検討する必要がありますが、保険料も継続的な負担となります。
次世代へ負担を継承することになる
売れない土地の問題は、自分の代で解決しなければ次の世代に引き継がれてしまいます。子どもや孫にとって、価値のない土地の固定資産税や管理責任を負わせることは、大きな負担となるでしょう。
時間が経過するほど土地の価値は下がり、売却はより困難になる傾向があります。早期の対策が、将来世代への責任でもあるのです。
相続した土地が売れない7つの典型的な理由
なぜ相続した土地が売れないのでしょうか。市場で敬遠される土地には、7つの共通する特徴があります。
● 狭小地や不整形地
● 再建築不可物件
● 立地条件の悪さ
● 境界未確定の土地
● 法的制限のある土地
● 地盤や環境の問題
● 不動産会社の優先順位の低さ
なぜこれらの土地が敬遠されるのか、その理由を詳しく解説します。
狭小地や不整形地
面積が狭すぎたり、形状が悪かったりする土地は、建物の建築が困難なため買い手がつきにくくなります。
特に、間口が狭い土地や三角形の土地、高低差の激しい傾斜地などは、建築コストが高くなるため敬遠されがちです。また、建築基準法上の制限により、実際に建物を建てられる面積が著しく少なくなる場合もあります。
建設コストが高い土地や建築基準法によって制限が設けられる土地は、一般的な土地よりも評価が低くなりがちで、敬遠されることを覚えておきましょう。
再建築不可物件
建築基準法の道路要件を満たしていない土地では、既存建物を取り壊すと新しい建物を建てることができません。
幅員4メートル未満の道路にしか接していない土地や、そもそも建築基準法上の道路に接していない土地がこれに該当します。また、再建築不可の土地は、住宅ローンの対象外となることが多く、現金購入できる買い手に限定されてしまうのです。
よって、高い評価が得られないため、土地が売れないという状況が生まれてしまうのです。
立地条件の悪さ
交通アクセスが悪い、商業施設や公共施設から遠い、治安が悪いといった立地条件の土地は、需要が限定的になります。人が住みづらいことや、生活における利便性が良くない点が、減点となる要因です。
最寄り駅から徒歩20分以上かかる土地や、バス便のみでアクセスが不便な地域の土地は、特に売却が困難です。過疎化が進む地方の土地では、人口減少に伴い需要そのものが減少している場合もあります。
上記はあくまでも例であるものの、該当する土地はなかなか売れない可能性が高いと思っておきましょう。
境界未確定の土地
隣地との境界が明確でない土地は、購入後にトラブルが発生するリスクがあるため、買い手から敬遠されます。境界が未確定の場合、近隣とのトラブルの原因になる可能性があるためです。
境界確定には測量費用として数十万~数百万円かかることがあり、さらに隣地所有者との協議が難航する場合もあります。売却前に境界確定を行うか、境界未確定のまま価格を下げて売却するかの判断が必要になるでしょう。
法的制限のある土地
都市計画法や建築基準法による厳しい制限がある土地は、活用の自由度が低いため市場価値が下がります。法的制限がある土地とは、具体的には以下の土地が該当します。
● 市街化調整区域の土地
● 農地
● 保安林 など
これらの土地は用途が制限されているため、一般的な住宅用地としての需要は期待できません。開発許可を得ることができれば活用可能な場合もありますが、手続きが複雑で時間もかかります。このような土地も、評価が低くなりがちで、なかなか売れない土地になってしまうのです。
地盤や環境の問題
軟弱地盤や土壌汚染、水害リスクの高い土地は、建築時の追加費用が発生するため買い手がつきにくくなります。建築前にこれらのリスクの対策を実施しなければならないため、通常の土地よりも評価が低くなってしまうのです。
地盤改良工事に数百万円かかる可能性がある土地や、過去に工場があった土地で土壌汚染の疑いがある場合、購入検討者は慎重になります。ハザードマップで災害リスクが高いとされている地域の土地も同様です。
水害リスクについてはハザードマップなどで確認できますが、土壌汚染については確認できる手段が限られています。必要であれば土壌汚染状況調査を実施し、汚染の有無を特定してもらいましょう。
不動産会社の優先順位の低さ
不動産会社にとって売却しやすい物件ではない場合、営業活動の優先順位が下がってしまうことがあります。
仲介手数料が低い安価な土地や、売却に時間がかかりそうな条件の悪い土地は、他の物件と比較して積極的な販売活動が行われない可能性があります。複数の不動産会社に相談することで、より積極的に取り組んでくれる会社を見つけることが重要です。
不動産会社が、自社にとって利益率の高い土地の売買を優先するのは仕方のないことです。条件の悪い土地は、不動産会社の優先順位も高くならないため、なかなか売却できない恐れがあるでしょう。
売れない土地を手放すための8つの対処法
売れない土地であっても、適切な対処法を選択すれば手放すことができます。以下の方法を状況に応じて検討してみましょう。
● 売却条件を見直す
● 土地の活用と収益化を目指す
● 不動産買取業者を活用する
● 不動産会社を変更変える
● 寄付で土地を処分する
● 空き家バンクに登録する
● 相続放棄を検討する
● 相続土地国庫帰属制度を利用する
それぞれの詳細を解説します。
売却条件を見直す
まずは現在の売却条件を見直し、市場に受け入れられやすい条件に変更することを検討します。
価格設定が市場相場と乖離している場合は、適正価格への調整が必要です。不動産鑑定士による査定を受けて、客観的な市場価値を把握しましょう。また、売却期限を設けず、長期的な視点で売却活動を継続することも重要です。
境界確定や測量といった売却準備に投資することで、買い手の不安を解消し、売却確率を高められる場合があります。
土地の活用と収益化を目指す
売却が困難な場合でも、土地を活用することで収益を得られる可能性があります。
立地条件によっては、駐車場経営や資材置き場としての賃貸、太陽光発電設備の設置といった活用方法が考えられます。初期投資は必要ですが、継続的な収入を得ることで固定資産税などの維持費用をカバーできるかもしれません。
ただし、投資回収期間や収益性については、事前に十分な検討が必要です。
不動産買取業者を活用する
一般的な仲介では売却が困難な土地でも、専門の買取業者であれば買い取ってもらえる可能性があります。
買取業者は転売や活用を前提として土地を購入するため、一般の買い手が敬遠する条件の土地でも対応してもらえるかもしれません。買取価格は市場価格より低くなることが一般的ですが、確実に手放すことができるメリットがあります。
複数の買取業者に査定を依頼し、条件を比較検討することが重要です。
不動産会社を変更変える
現在依頼している不動産会社で売却が進まない場合は、他の会社への変更を検討しましょう。
地域に特化した地元の不動産会社や、難しい物件の売却実績が豊富な会社であれば、異なるアプローチで売却できる可能性があります。一般媒介契約で複数の会社に同時に依頼することも有効な方法です。
インターネットでの物件紹介方法や営業手法が会社によって異なるため、より効果的な販売活動を行ってくれる会社を見つけることが重要です。
寄付で土地を処分する
売却が困難な土地であっても、寄付であれば受け入れてもらえる場合があります。
自治体への寄付が最も一般的ですが、公共性や地域の需要がある場合に限定されます。宗教法人や NPO 法人、近隣住民への寄付も選択肢として考えられるでしょう。寄付の場合、贈与税は受贈者が負担することになりますが、寄付者側では所得税の軽減措置を受けられる場合があります。
ただし、寄付先の選定や手続きには専門的な知識が必要なため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
空き家バンクに登録する
自治体が運営する空き家バンクに登録することで、移住希望者や地域での土地利用を検討している人に情報を届けることができます。
空き家バンクは主に建物付きの物件を対象としていますが、自治体によっては土地のみの登録も可能です。移住促進策として補助金制度を設けている自治体もあるため、買い手にとってメリットのある条件を提示できる場合があります。
登録費用は基本的に無料であり、リスクなく試すことができる方法です。
相続放棄を検討する
相続開始から3ヶ月以内であれば、相続放棄によって土地の所有権を放棄することができます。
ただし、相続放棄は全ての相続財産を放棄することになるため、プラスの財産がある場合は慎重な判断が必要です。また、相続人全員が相続放棄を行った場合でも、管理義務は残る点に注意してください。
相続放棄を検討する際は、家庭裁判所での手続きが必要になるため、司法書士や弁護士に相談することが重要です。
相続土地国庫帰属制度を利用する
2023年4月から開始された相続土地国庫帰属制度は、一定の要件を満たす土地を国に引き渡すことができる新しい制度です。
制度を利用するためには、土地が更地であること、担保権が設定されていないこと、境界が明確であることなどの要件を満たさなければなりません。また、審査手数料として14,000円、承認された場合の負担金として20年分の土地管理費相当額を納付する必要があります。
手続きは法務局で行い、申請から承認まで半年から1年程度の期間がかかります。すべての土地が対象になるわけではありませんが、要件を満たす土地であれば有効な選択肢となります。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって土地を取得した人が、一定の要件を満たした場合に土地を国に引き渡すことができる制度です。
所有者不明土地の発生を防止し、土地の適切な管理を促進することを目的として創設されました。相続以外の方法で取得した土地は対象外となるため注意が必要です。
申請ができる土地には厳格な要件が設定されており、以下に該当する土地は申請ができません。
● 建物がある土地
● 担保権や使用収益権が設定されている土地
● 他人の利用が予定されている土地
● 土壌汚染されている土地
● 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
● 建物がある土地
● 担保権や使用収益権が設定されている土地
● 他人の利用が予定されている土地
● 土壌汚染されている土地
● 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
申請は、最初に管轄の法務局で事前相談を行い、申請可能性を確認します。その後、申請書類を作成して正式に申請を行います。法務局による書面審査と実地調査が実施され、承認可否が決定されるのです。申請書や土地の登記事項証明書、地積測量図、境界確定に関する書類、土地の利用状況を示す書類などを用意しておきましょう。
審査手数料として、土地1筆につき14,000円が必要です。承認された場合は、20年分の土地管理費相当額を負担金として納付する必要があります。負担金の額は土地の種類や面積によって異なりますが、最低でも20万円程度となります。
申請から承認まで半年から1年程度の期間を要するため、余裕をもって手続きを進めることが重要です。
専門家への相談が重要な理由
売れない土地の問題は、法律、税務、不動産取引など多角的な知識が必要な複雑な問題です。そのような場合は、司法書士をはじめとする専門家に相談しましょう。
司法書士は相続登記や相続放棄の手続きを専門としており、土地の法的な問題について適切なアドバイスを提供できます。相続土地国庫帰属制度の申請についても、必要書類の準備から申請手続きまでサポートしてもらえます。複雑な権利関係の整理や境界確定に関する問題についても相談可能です。
また、土地の処分方法によって税務上の取り扱いが大きく異なるため、税理士への相談は欠かせません。
売却した場合の譲渡所得税や寄付した場合の税務処理、相続税の申告における土地の評価方法など、専門的な知識が必要な分野です。適切な税務処理を行うことで、税負担を最小限に抑えることができます。
土地の適正価格や売却可能性の判断には、不動産の専門知識も必要になるでしょう。
不動産鑑定士による評価や、土地家屋調査士による測量・境界確定、不動産コンサルタントによる活用提案など、それぞれの専門家が異なる観点からアドバイスをうけてください。
まとめ
相続した土地が売れない問題は、放置すればするほど深刻化していきます。固定資産税の負担、管理責任、損害賠償リスクなど、多くの問題を抱えることになります。しかし、適切な対処法を選択すれば、売れない土地であっても手放すことは可能です。
そもそも、売れない土地の問題は複雑で専門的な知識が必要です、早期に司法書士、税理士、不動産の専門家に相談することをおすすめします。適切な専門家のサポートを受けることで、あなたの状況に最適な解決策を見つけることができるでしょう。
ひろしま相続・不動産ホットラインでは、相続専門の税理士や不動産鑑定士が在籍する事務所です。6名の専門家にて、相続におけるトラブルを事前に防止するお手伝いができます。相続について不安がある方は、ぜひひろしま相続・不動産ホットラインにご連絡ください。