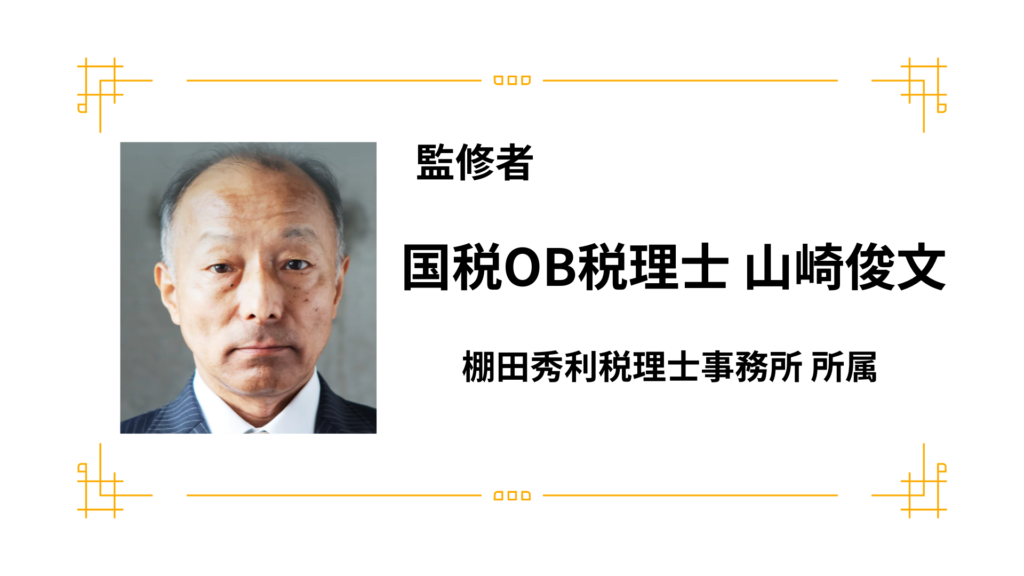相続税の追徴課税は申告漏れや納税遅延で発生|納税猶予制度も解説
相続税の追徴課税とは、相続税の納期限内に納付されなかった場合や、実際の相続税よりも申告した税額が少なかったと発覚した場合などに、追加で納める税金です。相続税を納めてほっとしたところに、追徴課税の通知を受けて青ざめる事態は避けたいですよね。
この記事では、どのような場合に相続税の追徴課税が発生するかを解説。追徴課税への対処方法も紹介します。追徴課税を事前に避けたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
相続税の追徴課税は申告や納付の不備が発覚した場合に支払う税金
相続税の追徴課税とは、相続税の申告や不備が発覚した場合に支払う税金です。令和5年度においては、追徴課税の額は合計654億円にも上っています。1件当たりの申告漏れ課税価格は4,156万円となり、過去最高を記録しました。さらに1件当たりの追徴課税額は1,043万円と、初めて1,000万円を超える水準となっています。
そのおもな原因は、確定申告の誤りや漏れ、納税漏れ、資産評価の誤りなど。税務調査される割合は約20%(5件に1件の割合)ですが、その約9割が追徴課税となっているデータもあります。知識不足のために追徴課税の対象になっていることもあるため注意しましょう。
特に近年は、デジタル化の進展により税務署の調査能力が向上しており、海外資産や暗号資産(仮想通貨)の申告漏れも発覚しやすくなっています。また、マイナンバー制度により預金口座の情報も把握されやすくなっているため、より一層の注意が必要です。
参照:国税庁|令和5事務年度における相続税の調査などの状況
相続税の追徴課税は4種類
相続税の追徴課税は4種類あり、下記のとおりです。
● 延滞税
● 過少申告加算税
● 重加算税
● 無申告加算税
なかには早く対応しなければ、納税金額が増えてしまうケースもあります。
延滞税
相続税の申告期限から納付期限までの間に納付しなければ、延滞税が課せられます。納期限から2カ月以上経過すると利率が大きく跳ね上がるため注意が必要です。日を追うごとに、額が膨らんでいくため1日でも早く納付しましょう。
延滞税の計算は次のとおりです。
| 期間 | 税率 |
| 納期限の翌日から2カ月を経過する日まで | 年7.3%もしくは特例基準割合+1%のいずれか低い割合 |
| 納期限の翌日から2カ月を経過する日の翌日以降 | 年14.6%もしくは特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合 |
特例基準割合は、財務大臣が年に1度告知する割合に基づき決定しています。令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間は年2.4%、2カ月以降の特例基準割合は年9.7%です。令和7年も同水準で推移すると予想されています。
滞納すると、財産に対して次のような処分を受ける場合があります。
● 差押
● 換価
● 配当
差押えは、有価証券や現預金が対象です。換価は、おもに不動産が対象で、多くの場合は公売にかけられます。なお、令和6年度から電子納税の推進により、e-Taxやダイレクト納付を利用した場合は、延滞税の計算において優遇措置が設けられる場合があります。
参照:国税庁|No.9205 延滞税について
過少申告加算税
過剰申告加算税とは、申告納税額が過少であると判明した場合に課される税の一種です。税率は10~15%となっています。
本来納付すべき税金との差額を納める際に、過少申告加算税の10%を加算。ただし、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%を加算となっています。自主的に修正申告を行った場合は、過少申告加算税は課税されません。
ただし、令和6年1月以降、税務調査の事前通知を受けてから修正申告を行った場合は、5%または10%の過少申告加算税が課される場合があるため、より早期の自主的な修正申告が重要となっています。
重加算税
重加算税とは、本来納税すべき事実を偽ったり隠蔽したりしたことが判明した場合に課せられる税金で、税率は35~40%です。また、期限内に納税申告書を提出しなかった場合は、延滞税とともに、基礎となるべき納税額に40%分が追加で課されます。
過去5年以内に重加算税や無申告加算税が課されていた場合は、上記の税額に10%上乗せされるので注意しましょう。
過去5年以内に重加算税や無申告加算税が課されていた場合は、上記の税額に10%上乗せされるので注意してください。さらに、令和5年度からは悪質な事案に対しては、過去10年間の取引履歴まで遡って調査される可能性があります。
無申告加算税
無申告加算税とは、正当な理由なしに申告期限までに申告しなかった場合に課税される税金です。税率は5~20%です。
調査通知前までに申告すれば5%、通知後から調査による更正など予知前までなら10%(15%)、調査による更正など予知以後であれば15%(20%)となっています。
なお、令和6年度からは、無申告に対する取り締まりが強化されました。特に高額な無申告案件(納税額300万円超)については、無申告加算税の税率が最大30%まで引き上げられる場合があります。
相続税の追徴課税は税務調査で見つかるケースが多い
相続税の追徴課税の多くは、税務調査で見つかっています。税務調査とは、申告が正しくされているかを調べるもので、申告に誤りがあることなどが想定される場合に行われます。具体的には、申告書の内容と帳簿が一致しているか、適切な税額が計算されているか、税法に則した控除が計上されているかなどです。
税務調査が行われる時期は、特に決まっていませんが、一般的に3月の確定申告が終わった4~5月頃、もしくは税務署や国税局の人事異動のあとの7月~11月ごろに行われることが多いようです。
近年では、税務署のAI活用により、申告内容の不審な点を自動的に検出するシステムが導入されており、より効率的かつ精度の高い調査対象の選定が行われています。特に、KSK(国税総合管理)システムの高度化により、過去の申告データとの整合性チェックが強化されているのです。
さかのぼって追徴課税が行われる期間は、原則5年と法律で決められています。これは相続税の税務調査の時効が5年とされているためです。そのため、帳簿や領収書などの資料も5年分をとっておきましょう。また、意図的に脱税していた場合は、時効は7年に延長されます。
相続税の税務調査で追徴課税を受けやすい5つのケース
相続税の税務調査で追徴課税を受けやすいケースを5つ紹介します。
● 預貯金が多く死亡直前に多額の現金が下ろされている場合
● 生前贈与の可能性がある場合
● 不動産の評価間違いや申告漏れがある場合
● 多額の借入金があるのに相続財産がない場合
● 保険の計上漏れがある場合
順にみていきましょう。
預貯金が多く死亡直前に多額の現金が下ろされている場合
相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の預金口座は凍結されます。そのため、葬儀費用などに備えて、死亡直前に被相続人の口座から現金を引き出すこともあります。この場合、引き出した現金も含めた申告が必要です。税務署は、死亡直前のお金の動きをチェックしているので、うっかり申告し忘れなどがないようにしましょう。
特に、死亡前3年以内の預金の動きは重点的に調査されます。また、令和6年度からは金融機関の協力体制が強化され、100万円以上の現金引き出しについては、税務署への報告が義務化される方向で検討されています。十分注意してください。
生前贈与の可能性がある場合
相続税調査では、亡くなった本人の名義だけでなく、家族名義の財産もチェックされます。被相続人(亡くなった人)が家族名義の口座を作って、多額のお金を貯めていた場合などは要注意です。家族名義の財産が収入と比較して明らかに多い場合は、生前贈与の可能性があると判断されます。
令和6年1月から、相続開始前7年以内の生前贈与について相続財産に加算する制度が始まりました(従来は3年以内)。これにより、より長期間の贈与履歴が調査対象となるため、過去の贈与についても正確に把握しておく必要があります。
不動産の評価間違いや申告漏れがある場合
不動産の評価間違いや申告漏れがあり、相続税が本来よりも低い金額になっていた場合、税務調査で追徴課税となるケースがあります。不動産の評価は、高額になりやすいため、税額が大きく変動するでしょう。
令和5年度から、路線価と実勢価格の乖離が大きい地域については、税務署が独自の補正率を適用する場合があります。特に、タワーマンションの評価については、令和6年1月から新しい評価方法が導入され、従来よりも評価額が高くなるケースが増えているのです。
多額の借入金があるのに相続財産がない場合
借入金に見合った相続財産がない場合、借入金の使用目的を明らかにする目的で税務調査が入る場合もあります。その理由として、多額の借入金をもとにして不動産を購入しているのではないかと考えられるためです。不動産などに使用していないとしても、借入金の使用目的をはっきりさせるため調査が行われます。
近年では、相続対策として行われた借入による不動産購入について、租税回避行為と認定されるケースが増えています。特に、相続開始直前の借入については、その経済的合理性が厳しく審査されます。
保険の計上漏れがある場合
保険は契約者や被保険者、保険金の受取人などの状況によって、相続税の対象となるかどうかが変わります。相続税の課税対象になる死亡保険金は、支払った保険料の全部または一部を被相続人が負担していたケースです。
すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、非課税限度額を超えると、超過分に相続税が課税されます。それを踏まえた死亡保険金の非課税限度額の計算式は次のとおりです。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
相続人一人一人に課税される金額は、次の算式が適用されます。
相続人が受け取った生命保険金-非課税限度額×(受け取った生命保険額/生命保険金合計額)=各人に課税される生命保険金額
この計算が適切に行われていなかった場合は、計算しなおして追徴課税が発生するかもしれません。なお、法定相続人の数は、相続放棄した人がいても、放棄人も数に含まれます。
また、令和5年度からは、変額保険や外貨建て保険についても評価方法が明確化され、為替レートの適用時期なども厳格に定められているのです。特に、相続開始時点の為替レートを使用することが義務付けられました。
参照:国税庁|相続税の課税対象になる死亡保険金
相続税の追徴課税は相続人全員に連帯納付義務がある
相続人のうち1人が追徴課税を支払えない場合、相続人全員に連帯納付義務が生じます。滞納者に税務署から督促したにもかかわらず納税されない場合、ほかの相続人に「完納されていない旨のお知らせ」といった書面が届いて初めて気づくことが多いようです。この時点では、まだ納税は求められていません。相続人同士で話し合い、納税を促しましょう。
通知から2カ月を経過しても完納されない場合は、連帯納付義務者に督促状が届きます。その後は、連帯納付義務者も滞納処分の対象となってしまうので注意しましょう。基本的に相続税は、相続財産の一部を相続税の納付にあてれば足りるはずです。しかしほかの相続人の相続税まで納付するとしたら、足りなくなる可能性もあるでしょう。支払えない場合は財産の差し押さえなどが行われる可能性もあるため、すぐに対処する必要があります。
なお、令和4年度から連帯納付義務の範囲に一定の制限が設けられ、申告期限から5年を経過した場合や、延納・物納の許可を受けた場合は、連帯納付義務が解除されることになりました。ただし、これは本税についてのみで、追徴課税については引き続き連帯納付義務が継続します。
追徴課税の支払いは現金のみで免責もない
連帯納付義務は、現金一括の納付が原則です。「延納」や「物納」などを利用できない点も留意しておきましょう。自己破産したとしても税金の支払いは免責されません。
相続税の納期限から5年が経過すると時効となりますが、督促を受けた場合、時効は中断されてしまいます。連帯納付義務から外れるための手段は、相続放棄しかありません。その場合は、原則として相続開始日から3カ月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。遺産分割協議の席で「相続放棄します」と宣言しても法的効力はないため注意しましょう。
ただし、令和5年度から、特別な事情がある場合には、相続開始を知ってから3カ月を経過した後でも相続放棄が認められるケースが増えているのです。例えば、多額の追徴課税が後から判明した場合などは、家庭裁判所に事情を説明することで、相続放棄が認められる可能性があります。
さらに連帯納付義務を負ったまま、相続人が亡くなると、その納付義務は家族に相続されてしまいます。このように、連帯納付義務の問題は、多くのトラブルを生むため、対処に悩んだら専門家に相談するようにしましょう。
追徴課税を一括で支払えない際に納税猶予制度が利用できることもある
相続税の追徴課税が支払えない場合、猶予制度が利用できます。それが次の2種類です。
● 換価の猶予
● 納税の猶予
順に解説いたします。
換価の猶予
換価の猶予とは、税金を納付するのが困難な理由がある場合、税務署に申請することで認められる制度です。納付延滞により差し押さえられた財産を換金して納付する、新たに財産が差し押さえられるのを猶予してもらうなどです。ただし適用には、次の要件すべてに該当する必要があります。
● 納付により事業の継続や生活の維持が困難だと認められること
● 納税に誠実な意思を有すると認められること
● 対象となる相続税以外の国税の滞納がないこと
● 納付すべき期限から6カ月以内に申請書が提出されていること
● 原則として担保の提供があること
担保は、追徴課税額が100万円以下である場合や猶予を受ける期間が3カ月以内の場合は必要ありません。猶予を受けられる期間は1年以内で、期間中に毎月分割して納付していきます。期限内に完納がどうしても難しい場合は、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内で延長が認められるケースもあります。
令和6年度からは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対する特例措置は終了しましたが、物価高騰などの経済情勢を考慮した柔軟な運用が行われるようになりました。特に、中小企業や個人事業主については、より緩やかな要件で猶予が認められる場合があります。
参照:国税庁|国税を期限内に納付できないとき
納税の猶予
納税の猶予は、次の要件のいずれかに該当したら、原則として1年以内の猶予が認められる場合があります。
● 財産について災害や盗難に遭った
● 納税者や家族が病気になったもしくは負傷した
● 事業を廃業や休業した
● 事業に著しい損失を受けた
● 本体の期限から1年以上経過したあとに、修正申告などにより納付すべき税金が確定した
また、令和6年度からは、上記に加えて以下の事由も猶予の対象として明確化されました。
● サイバー攻撃により事業に重大な被害を受けた場合
● 感染症の流行により事業活動が著しく制限された場合
● 自然災害により間接的な被害(サプライチェーンの寸断など)を受けた場合
さらに、申請書が提出されており、担保の提供があることも条件です。担保についての条件や猶予期間の延長に関しては、換価の猶予と同様です。
追徴課税の対象にならないように相続税申告は税理士に相談を
最初に紹介したように、令和3年の1件当たりの追徴課税額の平均は886万円と高額でした。納付が終わり、ホッとしているときに追加支払いの通知が来るのは、非常に厄介ですよね。一括現金で支払うといった条件も、現金が手元にないと慌ててしまいます。そもそも追徴課税の対象にならないよう、正しく相続財産を評価し、申告することが重要でしょう。
とくに不動産は評価が難しい財産であり、かつ高額のため、申告漏れから来る追徴課税額も大きくなりがちです。それを避けるためには、信頼できる税理士に相談し、正しく相続税申告を行うようにしましょう。
ひろしま相続・不動産ホットラインでは、難しい不動産の評価もお任せください。相続専門の税理士と不動産鑑定士がスムーズな相続をお手伝いします。電話とWebのどちらでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。